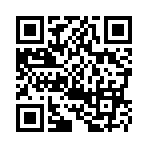2013年12月26日
「日要上人 第五百遠忌」 レポート
「日要上人 第五百遠忌」に参列してきました('ω')
この日のために県内外から集結した僧侶たちによる法要にはじまり、最後は一社二寺(鉾島神社/観音寺[曹洞宗]/妙国寺[日蓮宗])による“経”と“祝詞”の唱和、“南無妙法蓮華経”の中での玉串奉納・・・
宗教・宗派を超えた祈りの姿、町の結集に鳥肌の連続。この機会に立ち会うことができて、本当に感激でした。
きっと、ほとんどの方が「日要上人て誰やねん!?」て感じだと思いますが、亡くなってから500年も語り継がれるということは、本当にすごい方なのだということを改めて実感しました。
日要上人は細島出身で、日蓮宗の本山「妙本寺」の第十一代座主となった偉人です。
今回、その偉業とともに知っていただきたいと感じた“本門寺”というお寺の話をご紹介します。
日要上人は勤皇家としても知られ、当時朝廷に謁見することが許された数少ない人物のひとりでもありました。
妙本寺には、日要上人が天皇から賜った論旨(手紙のようのもの)が今も残されており、千葉県の文化財に指定されています。
そこには“お手紙ありがとう、またご意見をどんどんください、私のことをいつも思ってくれてありがとう”といった内容が綴られており、「恐恐謹言」という言葉で結ばれています。これは目下の人から目上の人に“おそれながらつつしんで申し上げる”の意。
天皇はあまり使わない言葉が日要上人には使われているのです。
その綸旨の中で天皇は、“妙本寺の日要上人”に対して“本門寺の日要上人”と表現していますが、実は“本門寺”とは実在しないお寺。
かつて、日本に仏教が伝わった拠点として東大寺・大宰府・薬師寺がありましたが、古い開眼は役に立たないということで、桓武天皇の時代に比叡山延暦寺が正式な開眼として仏教の拠点になりました。
しかし、ここでも鎌倉時代になって分派統合が行われ、これではいけないと、すべての仏法・世界の宗教思想が和合して一つの大いなる聖地を目指そうと言って、その理想の聖地を「本門寺」と名付けました。
ですから、本門寺というお寺は、当時はもちろん未だもってできていません。
天皇が日要上人に対して“本門寺の日要上人”と表現したのは、もし本門寺ができたらそこの住職にふさわしいと考えていたことを意味しています。
今回、日要上人の五百遠忌に際して、宗教・宗派を超えた取組ができたということは因縁とも呼べることであり、また次なる五百年、新たな時代の幕開けを感じさせるものとなったような気がしました!

この日のために県内外から集結した僧侶たちによる法要にはじまり、最後は一社二寺(鉾島神社/観音寺[曹洞宗]/妙国寺[日蓮宗])による“経”と“祝詞”の唱和、“南無妙法蓮華経”の中での玉串奉納・・・
宗教・宗派を超えた祈りの姿、町の結集に鳥肌の連続。この機会に立ち会うことができて、本当に感激でした。
きっと、ほとんどの方が「日要上人て誰やねん!?」て感じだと思いますが、亡くなってから500年も語り継がれるということは、本当にすごい方なのだということを改めて実感しました。
日要上人は細島出身で、日蓮宗の本山「妙本寺」の第十一代座主となった偉人です。
今回、その偉業とともに知っていただきたいと感じた“本門寺”というお寺の話をご紹介します。
日要上人は勤皇家としても知られ、当時朝廷に謁見することが許された数少ない人物のひとりでもありました。
妙本寺には、日要上人が天皇から賜った論旨(手紙のようのもの)が今も残されており、千葉県の文化財に指定されています。
そこには“お手紙ありがとう、またご意見をどんどんください、私のことをいつも思ってくれてありがとう”といった内容が綴られており、「恐恐謹言」という言葉で結ばれています。これは目下の人から目上の人に“おそれながらつつしんで申し上げる”の意。
天皇はあまり使わない言葉が日要上人には使われているのです。
その綸旨の中で天皇は、“妙本寺の日要上人”に対して“本門寺の日要上人”と表現していますが、実は“本門寺”とは実在しないお寺。
かつて、日本に仏教が伝わった拠点として東大寺・大宰府・薬師寺がありましたが、古い開眼は役に立たないということで、桓武天皇の時代に比叡山延暦寺が正式な開眼として仏教の拠点になりました。
しかし、ここでも鎌倉時代になって分派統合が行われ、これではいけないと、すべての仏法・世界の宗教思想が和合して一つの大いなる聖地を目指そうと言って、その理想の聖地を「本門寺」と名付けました。
ですから、本門寺というお寺は、当時はもちろん未だもってできていません。
天皇が日要上人に対して“本門寺の日要上人”と表現したのは、もし本門寺ができたらそこの住職にふさわしいと考えていたことを意味しています。
今回、日要上人の五百遠忌に際して、宗教・宗派を超えた取組ができたということは因縁とも呼べることであり、また次なる五百年、新たな時代の幕開けを感じさせるものとなったような気がしました!

2013年11月07日
ご利益タクシー
日向にある「上日向(かみひゅうが)タクシー」さんと、11月3日に開催される「カムヤマトアートフェスティバル 日向大神楽」のコラボ企画として『“神”日向タクシー』を運行をすることになりました。
見た目は他のタクシーと全く同じですが、よく見ると行燈とボディの文字が“上”ではなく“神”。
日向市内、宮崎県内で1台のご利益タクシーです。
車体番号には、末広がりの「888」を採用しています。
イベントとあわせてこちらも注目してみてください♪
昨日21日が出発式で、11月3日の24時までは、カムヤマト開催記念として乗車された方に限定で「神日向乗車記念券」をお渡しいたします。
宮崎は今、古事記編さん1300年と日本書紀編さん1300年をつなぐ「記紀編さん1300年」。神話の地でこういった楽しみが増えるといいですね~
▼カムヤマトアートフェスティバル Facebookページ
https://www.facebook.com/comeyamato.hyg

見た目は他のタクシーと全く同じですが、よく見ると行燈とボディの文字が“上”ではなく“神”。
日向市内、宮崎県内で1台のご利益タクシーです。
車体番号には、末広がりの「888」を採用しています。
イベントとあわせてこちらも注目してみてください♪
昨日21日が出発式で、11月3日の24時までは、カムヤマト開催記念として乗車された方に限定で「神日向乗車記念券」をお渡しいたします。
宮崎は今、古事記編さん1300年と日本書紀編さん1300年をつなぐ「記紀編さん1300年」。神話の地でこういった楽しみが増えるといいですね~
▼カムヤマトアートフェスティバル Facebookページ
https://www.facebook.com/comeyamato.hyg

2013年11月07日
ラピタ
ちょっと更新が途絶えてしまいました。。先日の古代勉強会からもう一つ。
“巨石文化”を伝えていったのは、海洋民族だとされています。
海洋民族の一つ「ラピタ」は、本格的な航海技術をもって、河岸神殿を建てながら環太平洋をめぐっていきました。
その碑に記されていたのが「ス・メラ」という文字だそうです。
(「カムヤマトイワレヒコスメラミコト」のように、スメラとは天皇につけて敬意を示す接頭語)
さて、その海洋民族にとって“水”は大変貴重なものなので必ず押さえていました。
その方法とは、海から“ピラミッド”=山を見つける。そして河口の砂から地質を調べる。
古代の民は、水を枯らさないためには森が大切だということを知っていて、そのためにお宮を建てていったとのことです。
しかし今は道路を建設したりして、水取場と頂上が断絶されてしまっていたりするのですが…
ちなみに古代人たちが目指した、死の海を渡った先にある、水が絶えることのない、不老不死の水があると言われる「東海の蓬莱山」とは日本のことではないかと、古代巨石文化・ペトログリフ研究家の武内一忠さんは仰っています。
写真は、以前にお舟出クルーズで撮影した、日向のピラミッド・米の山。標高192mとそれほど高い山ではないのに、住民の人の記憶では、どんなに雨が少なくても水が枯れたことはないそうです。ここも古代人の水取場の目印だったかもしれませんね。

“巨石文化”を伝えていったのは、海洋民族だとされています。
海洋民族の一つ「ラピタ」は、本格的な航海技術をもって、河岸神殿を建てながら環太平洋をめぐっていきました。
その碑に記されていたのが「ス・メラ」という文字だそうです。
(「カムヤマトイワレヒコスメラミコト」のように、スメラとは天皇につけて敬意を示す接頭語)
さて、その海洋民族にとって“水”は大変貴重なものなので必ず押さえていました。
その方法とは、海から“ピラミッド”=山を見つける。そして河口の砂から地質を調べる。
古代の民は、水を枯らさないためには森が大切だということを知っていて、そのためにお宮を建てていったとのことです。
しかし今は道路を建設したりして、水取場と頂上が断絶されてしまっていたりするのですが…
ちなみに古代人たちが目指した、死の海を渡った先にある、水が絶えることのない、不老不死の水があると言われる「東海の蓬莱山」とは日本のことではないかと、古代巨石文化・ペトログリフ研究家の武内一忠さんは仰っています。
写真は、以前にお舟出クルーズで撮影した、日向のピラミッド・米の山。標高192mとそれほど高い山ではないのに、住民の人の記憶では、どんなに雨が少なくても水が枯れたことはないそうです。ここも古代人の水取場の目印だったかもしれませんね。

2013年07月23日
古代シュメール文明と米の山の共通点
先日、大御神社で5000年前のものだという古代文字が発見されました。それで今、大御神社で古代文字の勉強会が行われているとお聞きし、昨日3回目の講義に参加させていただきました。
これまでの知識に全くない情報で四苦八苦しながらお聞きしたところでしたが、本当に面白くて面白くて一部だけでもお伝えしたいと思います(間違いがあったらごめんなさい…焦)。
■古代シュメール文明と米の山の共通点
シュメールとは、初期のメソポタミア文明で、チグリス川とユーフラテス川の間に栄えたとされています。そのシュメールにとって日本は交易の範囲内にあり、シュメールに影響を受けたと思われるものが多く日本に残っているということです。
シュメールの文明の中で、最高神は天神「アン」。象徴する記号は「米(※)」で、ピラミッドの頂上にはアンに米を供物として捧げました。
米の山の記事をあげた際にピラミッドというコメントをいただきましたが、まさに米の山は日向のピラミッドとしての役割を果たしていたのかもしれません。
ちなみに「アン」の長男である「エンソル」から来る「江良」という地名も日本各地に残っているそうですが、米の山の住所である日知屋の隣の隣が江良です。
ここはカワノの勝手な妄想ですが、日知屋と江良の間に「曽根」もあります。「江良+曽根」で「エンソル」と捉えられなくはないでしょうか…
蛇足ですが、旧約聖書において、飢饉の際にモーゼが神に祈ると天から「マナ」が降り注ぎました。これが米であり、結婚式でやる“ライスシャワー”の由来だそうです。
ユダヤ人が最終的につくったのはアメリカですが、americaは「an+rice」、そして偶然にも日本語では米と表記されます('Д')
しばらくの間、シュメールにドキドキな日々が続きそうです…
写真は本殿の裏に発見されたシュメール文字「ジャスラ」。ヘビを化身とする大地の守り神だそうです。見えるでしょうか?古代に思いをはせつつ、探してみてください。
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

これまでの知識に全くない情報で四苦八苦しながらお聞きしたところでしたが、本当に面白くて面白くて一部だけでもお伝えしたいと思います(間違いがあったらごめんなさい…焦)。
■古代シュメール文明と米の山の共通点
シュメールとは、初期のメソポタミア文明で、チグリス川とユーフラテス川の間に栄えたとされています。そのシュメールにとって日本は交易の範囲内にあり、シュメールに影響を受けたと思われるものが多く日本に残っているということです。
シュメールの文明の中で、最高神は天神「アン」。象徴する記号は「米(※)」で、ピラミッドの頂上にはアンに米を供物として捧げました。
米の山の記事をあげた際にピラミッドというコメントをいただきましたが、まさに米の山は日向のピラミッドとしての役割を果たしていたのかもしれません。
ちなみに「アン」の長男である「エンソル」から来る「江良」という地名も日本各地に残っているそうですが、米の山の住所である日知屋の隣の隣が江良です。
ここはカワノの勝手な妄想ですが、日知屋と江良の間に「曽根」もあります。「江良+曽根」で「エンソル」と捉えられなくはないでしょうか…
蛇足ですが、旧約聖書において、飢饉の際にモーゼが神に祈ると天から「マナ」が降り注ぎました。これが米であり、結婚式でやる“ライスシャワー”の由来だそうです。
ユダヤ人が最終的につくったのはアメリカですが、americaは「an+rice」、そして偶然にも日本語では米と表記されます('Д')
しばらくの間、シュメールにドキドキな日々が続きそうです…
写真は本殿の裏に発見されたシュメール文字「ジャスラ」。ヘビを化身とする大地の守り神だそうです。見えるでしょうか?古代に思いをはせつつ、探してみてください。
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

2013年07月23日
日知屋
古代社会では、その日がどんな日であるかを知っている人が貴いとされました。台風がやってくる季節や田植えの時期が分かる、そういう特別な人こそが「日知り」。
これが聖人を表す「聖(ひぢり)」という言葉の語源です。
日向市の東端・日向岬にある、米の山周辺には「日知屋」という地名があります。また、米の山には太陽の運行を測っていたと思われる磐座(ストーンサークル)があります。
もしかすると、日知屋にはかつて“日を知る人”がいたのかもしれません。
そしてもう一つの不思議。太陽神アマテラスの孫、ニニギノミコトが天より降臨した高千穂のくしふるの峰と米の山を結ぶ直線が、冬至の日の出ラインとぴったり合っているとのこと。
周辺を海に囲まれ、標高192mから四方を見渡せる米の山は、ニニギノミコトが太陽のパワーを受け取るのに最適な地として目印としながら天降ってきたのかもしれません(注:個人的な妄想です)。
※画像、進行方向先に見えるのが米の山。
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

これが聖人を表す「聖(ひぢり)」という言葉の語源です。
日向市の東端・日向岬にある、米の山周辺には「日知屋」という地名があります。また、米の山には太陽の運行を測っていたと思われる磐座(ストーンサークル)があります。
もしかすると、日知屋にはかつて“日を知る人”がいたのかもしれません。
そしてもう一つの不思議。太陽神アマテラスの孫、ニニギノミコトが天より降臨した高千穂のくしふるの峰と米の山を結ぶ直線が、冬至の日の出ラインとぴったり合っているとのこと。
周辺を海に囲まれ、標高192mから四方を見渡せる米の山は、ニニギノミコトが太陽のパワーを受け取るのに最適な地として目印としながら天降ってきたのかもしれません(注:個人的な妄想です)。
※画像、進行方向先に見えるのが米の山。
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka