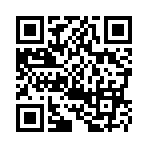2013年09月02日
「天与の使命である。」
美々津港横に立つ、海軍発祥の碑。
作者は彫刻家、故・日名子実三(ひなこじつぞう、1892年‐1945年4月25日、大分県臼杵市出身)。
八咫烏に導かれ、歴史に名を残した彫刻家でした。
この海軍発祥の碑は、神武天皇がお船出した(※)美々津の地は“日本海軍発祥之地”として、紀元二千六百年記念事業の一環で建立されたもの。
また、日名子実三は紀元二千六百年記念事業において、宮崎市の平和台公園にある「平和の塔」のデザインも手掛けています。(平和台のふもとに皇宮屋がある)
「平和の塔」は、元の名を「八紘之基柱(あめつちのもとはしら)」と言い、『日本書紀』で神武天皇が天皇に即位した際の「掩八紘而爲宇(あめのしたをおおひていえとなさむ、またよろしからずや=世界がひとつの屋根の下の家族のように仲良く暮らすなら、なんと楽しく嬉しいことだろう)」という詔に由来しています。
ちなみに平和の塔には手水舎がありますが、その水盤は日向市美々津産の岩を使用し、前面に当時の相川勝六知事の筆で「美々津」と彫られています。これは、神武天皇が美々津からお舟出したことを表しているということです。
日名子実三は基柱の提唱者である当時の宮崎県知事・相川勝六と出会い、基柱の話を受けて自ら「報酬は一文もいらないから、是非私にやらせてほしい」と申し入れました。
そして当時、新進の彫刻家であった日名子実三が手掛けることとなり、「これは天与の使命である。」と神助を得て渾身の仕事を行いました。
この後、日名子実三は日本サッカー連盟のシンボルマークとなっている、日本神話の中で神武天皇を道案内したと言われる鳥・八咫烏(やたがらす)をモチーフにしたエンブレムのデザインをしたことで知られます。
※宮崎県の高原で幼少期をすごした神武天皇は、15歳で皇太子となり宮崎市内の皇宮(宮崎神宮摂社)に宮を移すと、45歳のときに東遷に発ちます。そして陸路で美々津まで行き、そこで水軍を整えて再び進発したと伝えられています。

作者は彫刻家、故・日名子実三(ひなこじつぞう、1892年‐1945年4月25日、大分県臼杵市出身)。
八咫烏に導かれ、歴史に名を残した彫刻家でした。
この海軍発祥の碑は、神武天皇がお船出した(※)美々津の地は“日本海軍発祥之地”として、紀元二千六百年記念事業の一環で建立されたもの。
また、日名子実三は紀元二千六百年記念事業において、宮崎市の平和台公園にある「平和の塔」のデザインも手掛けています。(平和台のふもとに皇宮屋がある)
「平和の塔」は、元の名を「八紘之基柱(あめつちのもとはしら)」と言い、『日本書紀』で神武天皇が天皇に即位した際の「掩八紘而爲宇(あめのしたをおおひていえとなさむ、またよろしからずや=世界がひとつの屋根の下の家族のように仲良く暮らすなら、なんと楽しく嬉しいことだろう)」という詔に由来しています。
ちなみに平和の塔には手水舎がありますが、その水盤は日向市美々津産の岩を使用し、前面に当時の相川勝六知事の筆で「美々津」と彫られています。これは、神武天皇が美々津からお舟出したことを表しているということです。
日名子実三は基柱の提唱者である当時の宮崎県知事・相川勝六と出会い、基柱の話を受けて自ら「報酬は一文もいらないから、是非私にやらせてほしい」と申し入れました。
そして当時、新進の彫刻家であった日名子実三が手掛けることとなり、「これは天与の使命である。」と神助を得て渾身の仕事を行いました。
この後、日名子実三は日本サッカー連盟のシンボルマークとなっている、日本神話の中で神武天皇を道案内したと言われる鳥・八咫烏(やたがらす)をモチーフにしたエンブレムのデザインをしたことで知られます。
※宮崎県の高原で幼少期をすごした神武天皇は、15歳で皇太子となり宮崎市内の皇宮(宮崎神宮摂社)に宮を移すと、45歳のときに東遷に発ちます。そして陸路で美々津まで行き、そこで水軍を整えて再び進発したと伝えられています。

2013年07月23日
水
みず(水)はかつて「み」と言い、うみ(海)も「み」と言いました。
源流となるのが「み(水)」+「な(の)」+「もと(本)」。川から海へと流れ込む入口が「み(水)」+「な(の)」+「と(戸)」です。
神武天皇ご東遷の際に修祓の儀を行ったとされる、美々津港の河口を見渡す権現崎(立磐神社の対岸)にある「湊柱神社」(通称:権現さん)には、速秋津彦命(ハヤアキツヒコノミコト)が祀られています。
速秋津彦命(速秋津日子神)は、イザナギ・イザナミによる神生みで産まれた神。速秋津比売神(ハヤアキツヒメ)と合わせて男女一対で、二神の神生みの途中で河と海とを受け持ち、八柱の神を生みました。
これら八柱の神が司るものを見ていくと、川の上流、すなわち“みなもと”へと向かいます。
まず川と海がぶつかる場所で“泡”が立つ。川を遡ると、平らな“水面”が続く川になる。さらに上流へ進むと、“分水嶺”に至る。最後の源流として出てくるのは“汲みひさごを持った神様”で、この神様がどこからか水を汲んでくるのだと考えられました。
○泡―沫那藝神(アワナギノカミ)・沫那美神(アワナミノカミ)
○水面―頬那藝神(ツラナギノカミ)・頬那美神(ツラナミノカミ)
○分水嶺―天之水分神(アメノミクマリノカミ)・国之水分神(クニノミクマリノカミ)
○ひさご持ちの神―天之久比奢母智神(アメノクヒザモチノカミ)・国之久比奢母智神(クニノクヒザモチノカミ)
水が引き起こす様々な現象、そして川を脈々と流れてくる水が一体どこから来ているのか、その不思議に壮大な神々の仕業を想像した。水とともに暮らしてきた日本人の繊細でみずみずしい感性が感じられますね~(*´з`)
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

源流となるのが「み(水)」+「な(の)」+「もと(本)」。川から海へと流れ込む入口が「み(水)」+「な(の)」+「と(戸)」です。
神武天皇ご東遷の際に修祓の儀を行ったとされる、美々津港の河口を見渡す権現崎(立磐神社の対岸)にある「湊柱神社」(通称:権現さん)には、速秋津彦命(ハヤアキツヒコノミコト)が祀られています。
速秋津彦命(速秋津日子神)は、イザナギ・イザナミによる神生みで産まれた神。速秋津比売神(ハヤアキツヒメ)と合わせて男女一対で、二神の神生みの途中で河と海とを受け持ち、八柱の神を生みました。
これら八柱の神が司るものを見ていくと、川の上流、すなわち“みなもと”へと向かいます。
まず川と海がぶつかる場所で“泡”が立つ。川を遡ると、平らな“水面”が続く川になる。さらに上流へ進むと、“分水嶺”に至る。最後の源流として出てくるのは“汲みひさごを持った神様”で、この神様がどこからか水を汲んでくるのだと考えられました。
○泡―沫那藝神(アワナギノカミ)・沫那美神(アワナミノカミ)
○水面―頬那藝神(ツラナギノカミ)・頬那美神(ツラナミノカミ)
○分水嶺―天之水分神(アメノミクマリノカミ)・国之水分神(クニノミクマリノカミ)
○ひさご持ちの神―天之久比奢母智神(アメノクヒザモチノカミ)・国之久比奢母智神(クニノクヒザモチノカミ)
水が引き起こす様々な現象、そして川を脈々と流れてくる水が一体どこから来ているのか、その不思議に壮大な神々の仕業を想像した。水とともに暮らしてきた日本人の繊細でみずみずしい感性が感じられますね~(*´з`)
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

2013年07月23日
耳川
椎葉村に源を発し、美々津港から日向灘に注ぐ耳川。
東遷を決意した神武天皇は、舟出の準備をする場所として、河口が深く、ふんだんに木材が調達でき、また里人は良いとのことで耳川が流れ込む美々津港を舟出の地と決めました。
実は「耳」という名は神武天皇に縁が深く、子の名前には耳が入っています。
長男は手研耳命(タキシミミノミコト)
次男は研耳命(キシミミノミコト)
三男は日子八井命(ヒコヤイノミコト)
四男は神八井耳命(カムヤイミミノミコト)
五男で跡を継いだ第2代の綏靖(スイゼイ)天皇は神沼河耳命(カムヌナカワミミノミコト)
かつて舟出までの時を過ごした耳川の風景を思い出してその名をつけたのかもしれません。
ちなみに耳の語源は「身の中の実」。「目ー芽」「鼻ー花」「歯ー葉」「耳ー実実」と書くと分かりますが、これは偶然の一致ではなく、認識のプロセスを植物の成長と同じように表現していたことを表しています。つまり耳はプロセスの完結です。
また、「お聞きになる」の古語である「きこしめす」が“支配する・受容する”という意味を持っており、耳にはその能力があると考えられます。
耳という文字を入れたのは、大和平定を平定する、またはその支配が完了するという意味があったのでしょうか。
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

東遷を決意した神武天皇は、舟出の準備をする場所として、河口が深く、ふんだんに木材が調達でき、また里人は良いとのことで耳川が流れ込む美々津港を舟出の地と決めました。
実は「耳」という名は神武天皇に縁が深く、子の名前には耳が入っています。
長男は手研耳命(タキシミミノミコト)
次男は研耳命(キシミミノミコト)
三男は日子八井命(ヒコヤイノミコト)
四男は神八井耳命(カムヤイミミノミコト)
五男で跡を継いだ第2代の綏靖(スイゼイ)天皇は神沼河耳命(カムヌナカワミミノミコト)
かつて舟出までの時を過ごした耳川の風景を思い出してその名をつけたのかもしれません。
ちなみに耳の語源は「身の中の実」。「目ー芽」「鼻ー花」「歯ー葉」「耳ー実実」と書くと分かりますが、これは偶然の一致ではなく、認識のプロセスを植物の成長と同じように表現していたことを表しています。つまり耳はプロセスの完結です。
また、「お聞きになる」の古語である「きこしめす」が“支配する・受容する”という意味を持っており、耳にはその能力があると考えられます。
耳という文字を入れたのは、大和平定を平定する、またはその支配が完了するという意味があったのでしょうか。
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

2013年07月23日
住吉三神
美々津港にある立磐神社(たていわじんじゃ)は、海の神・住吉三神を祀り、神武天皇が航海の安全を祈願したと言われています。
住吉三神とは、底筒男命(そこつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)、表筒男命(うわつつのおのみこと)の総称。
イザナキが黄泉国での穢れを洗い清めるために禊を行ったとき、「上の瀬は大変流れが速い。下の瀬は大変流れが弱い」と言って、瀬の深いところですすいだときに生まれたのが底筒男命、中間で生まれたのが中筒男命、表面で生まれたのが表筒男命です。
すなわち海の深い部分、真ん中の部分、浅い部分を司る神様なのです。海をエリアじゃなくて深さで分けるという感性にまたもやノックアウトされました。
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

住吉三神とは、底筒男命(そこつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)、表筒男命(うわつつのおのみこと)の総称。
イザナキが黄泉国での穢れを洗い清めるために禊を行ったとき、「上の瀬は大変流れが速い。下の瀬は大変流れが弱い」と言って、瀬の深いところですすいだときに生まれたのが底筒男命、中間で生まれたのが中筒男命、表面で生まれたのが表筒男命です。
すなわち海の深い部分、真ん中の部分、浅い部分を司る神様なのです。海をエリアじゃなくて深さで分けるという感性にまたもやノックアウトされました。
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka