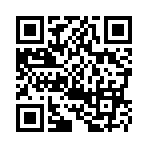2013年11月07日
龍神の吐息
先日、大御神社の古代勉強会〈最終回〉に参加してきました。
講師は今回も、熊本からお越しいただいた古代巨石文化・ペトログリフ研究家の武内一忠さん。
必死でメモを取ったら、約2時間の講義でA4のノート5ページがびっしり埋まりました。
前回に比べたら少しは理解できましたが、完全に頭がパンクしました~(;´Д`)
龍神の話が出てきて面白かったので、お伝えしたいと思います(※聞いたままではないので、想像が入ってるかもしれませんがご了承ください)。
「龍/dragon」は世界の様々な場所に伝説がありますが、どこも“退治する”とか“封じ込める”といった対象のようです。
しかしながら、吹き抜ける風や闇夜を漂う河の流れなど、体感的には“守り神”として考えているのも面白いところです。
龍は火山の象徴であり、雨をもたらす象徴です。
空にわっと雲がわいて、雷(いかずち)が鳴る。それは古代の人にとって恐ろしい存在でありながら、祈りを捧げると恵みの雨をもたらしてくれる有難い存在でもありました。
古代シュメール文明では、天神アン(=北極星)を最高神として崇めていました。当時の北極星はりゅう座の中にあって、アンが龍神を治めていると考えられていたということです。
最近、太平洋沖に太陽系最大の火山が見つかったと話題になっています。
太陽系最大の火山、すなわち超巨大な龍。大御神社を頭として、阿蘇の火山に続く龍神が共鳴していてもおかしくはありません。
“Breath of God”というのは、龍神の吐息。大地の気が揺れている、その目の前で大御神社の宮司は毎朝禊をして、その鳴動を感じ取っているはじめの人ではないかと武内さんは言ってます。
台風18号が大きな被害を残していきました。以前京都に住んでいたので、本当に信じられない光景でした。
龍のなす業なのでしょうか。そしてこの出来事は私たちに何を問いかけているのでしょうか。
被害にあわれた地域の皆さまには心からお見舞い申し上げます。
大御神社の本殿。武内さんはこの岸壁が龍の頭そのものだと言います。

講師は今回も、熊本からお越しいただいた古代巨石文化・ペトログリフ研究家の武内一忠さん。
必死でメモを取ったら、約2時間の講義でA4のノート5ページがびっしり埋まりました。
前回に比べたら少しは理解できましたが、完全に頭がパンクしました~(;´Д`)
龍神の話が出てきて面白かったので、お伝えしたいと思います(※聞いたままではないので、想像が入ってるかもしれませんがご了承ください)。
「龍/dragon」は世界の様々な場所に伝説がありますが、どこも“退治する”とか“封じ込める”といった対象のようです。
しかしながら、吹き抜ける風や闇夜を漂う河の流れなど、体感的には“守り神”として考えているのも面白いところです。
龍は火山の象徴であり、雨をもたらす象徴です。
空にわっと雲がわいて、雷(いかずち)が鳴る。それは古代の人にとって恐ろしい存在でありながら、祈りを捧げると恵みの雨をもたらしてくれる有難い存在でもありました。
古代シュメール文明では、天神アン(=北極星)を最高神として崇めていました。当時の北極星はりゅう座の中にあって、アンが龍神を治めていると考えられていたということです。
最近、太平洋沖に太陽系最大の火山が見つかったと話題になっています。
太陽系最大の火山、すなわち超巨大な龍。大御神社を頭として、阿蘇の火山に続く龍神が共鳴していてもおかしくはありません。
“Breath of God”というのは、龍神の吐息。大地の気が揺れている、その目の前で大御神社の宮司は毎朝禊をして、その鳴動を感じ取っているはじめの人ではないかと武内さんは言ってます。
台風18号が大きな被害を残していきました。以前京都に住んでいたので、本当に信じられない光景でした。
龍のなす業なのでしょうか。そしてこの出来事は私たちに何を問いかけているのでしょうか。
被害にあわれた地域の皆さまには心からお見舞い申し上げます。
大御神社の本殿。武内さんはこの岸壁が龍の頭そのものだと言います。

2013年08月03日
大御神社・龍神伝説 その三
新名宮司が、禊を始めて20年後の“おかげ”。
こちらは見ての通り。大御神社の摂社である「鵜戸神社」で見つかった昇り龍です。
洞窟の中から入口を振り返ると、差し込む光のシルエットがまさに天に昇らんとする龍の形をしています。
もちろん偶然にできた自然の造形ではなく、古代の龍神信仰の表れ。洞窟そのものが、龍神の神威を身につけるいわゆる“胎内くぐり”としての役割を持つそうです。
しかし、様々な英知を持った古代の人々とは言え、これだけ大きなものをどうやって彫ったのでしょうか。
元々小さな洞窟のようなものがあって、そこに霊的なものを感じた古代の人々が信仰の場所をつくったと予想されます。
中国などの古代石仏にも例があるとのことですが、入口上部から彫って広げて行ったのだろうということです。
確かに、下の方は丸く元々の形のようですが、上の方はギザギザとしており刻まれたような形をしています。
ではどんな道具を使って彫ったのかですが、基本的には硬い石を使いました。それで難しい場合は、木のくさびをいくつも打ち込んでその木に水をしみこませて膨らませて広げていったのだそうです。
長い長い時間をかけて作り上げたのですね。「そのような専任の仕事があったんでしょうか」と聞きましたら、自然とともに暮らしていた古代の人々にとって、“神々に祈りを捧げること”それがすべてだったのだと( ;∀;)
洞窟の前には龍のような大きな岩があり、今で言えば狛犬のようなシンボルと考えられます。「神話は自然への幻視から始まる(神話的想像力)」と言われますが、この岩と後ろにある洞窟を海から見たときに龍が洞窟から出てきたところを想像したのかもしれません。
ところでこの洞窟、実はお隣の伊勢ケ浜に貫通しているのではないかという話があります。
今は土や岩が被り、穴がどこに抜けているかは分からないそうですが、宮司の知り合いも含め、子供時代に探検していて偶然抜けてしまったという人が3人もいるそうです。
もしかすると近いうちに、歴史的大発見を目撃できるかもしれませんね。

▼「和く!和く!神ingネットワーク」Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka
こちらは見ての通り。大御神社の摂社である「鵜戸神社」で見つかった昇り龍です。
洞窟の中から入口を振り返ると、差し込む光のシルエットがまさに天に昇らんとする龍の形をしています。
もちろん偶然にできた自然の造形ではなく、古代の龍神信仰の表れ。洞窟そのものが、龍神の神威を身につけるいわゆる“胎内くぐり”としての役割を持つそうです。
しかし、様々な英知を持った古代の人々とは言え、これだけ大きなものをどうやって彫ったのでしょうか。
元々小さな洞窟のようなものがあって、そこに霊的なものを感じた古代の人々が信仰の場所をつくったと予想されます。
中国などの古代石仏にも例があるとのことですが、入口上部から彫って広げて行ったのだろうということです。
確かに、下の方は丸く元々の形のようですが、上の方はギザギザとしており刻まれたような形をしています。
ではどんな道具を使って彫ったのかですが、基本的には硬い石を使いました。それで難しい場合は、木のくさびをいくつも打ち込んでその木に水をしみこませて膨らませて広げていったのだそうです。
長い長い時間をかけて作り上げたのですね。「そのような専任の仕事があったんでしょうか」と聞きましたら、自然とともに暮らしていた古代の人々にとって、“神々に祈りを捧げること”それがすべてだったのだと( ;∀;)
洞窟の前には龍のような大きな岩があり、今で言えば狛犬のようなシンボルと考えられます。「神話は自然への幻視から始まる(神話的想像力)」と言われますが、この岩と後ろにある洞窟を海から見たときに龍が洞窟から出てきたところを想像したのかもしれません。
ところでこの洞窟、実はお隣の伊勢ケ浜に貫通しているのではないかという話があります。
今は土や岩が被り、穴がどこに抜けているかは分からないそうですが、宮司の知り合いも含め、子供時代に探検していて偶然抜けてしまったという人が3人もいるそうです。
もしかすると近いうちに、歴史的大発見を目撃できるかもしれませんね。

▼「和く!和く!神ingネットワーク」Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka
2013年08月03日
大御神社・龍神伝説 その二
龍の玉(ドラゴンボール)が発見された際の秘話。
境内拡張造成工事の後に見つかった神座(さざれ石)のそばで、いつも水がちょろちょろ流れ込み、泥がたまっている場所があったそうです。
新名宮司はこの場所が気になっていて、いつか堀ってみようと思っていましたが、いつも水浸しなので長年そのままになっていました。
しかし平成23年、正月から4月まで雨が一滴も降らず、完全に乾いた時がありました。それで今が機会だと、4月12日から14日の3日間をかけて掘り起こしてみました。
すると中から、長径1m・短径75㎝の卵型の大きな岩が出てきました。下の方に手を突っ込んでみると、どうやら球状になっている。取り出そうにも取り出せない(重さ推定1t)。一体これは何じゃろかい?と。
地質学的には甌穴と言われるものですが、側面には意図的に掘られたではないかと思われる渦巻き状のらせんがあります。
NPO法人「日本巨石文化研究所」の武内一忠氏によれば、丸石は“龍の卵”、貯まった水は“羊水”、すなわち龍神信仰の表れであるとのこと。
これが龍神伝説のはじまり。宮司が2頭の白龍を見た10年後の出来事です。
今は泥が取り除かれ、水の中に龍の玉が眠っていますが、このどこからかしみ出してきて甌穴に注がれる水。一体どこから来ているのだろうと思っていたら、大御神社の東側にある「櫛の山」が源流だったようです。
今は櫛の山と大御神社を道路が分断しているのでたくさんの水は流れてきませんが、以前はもっと脈々と水が流れていたのだろうと言われます。
これはすなわち龍神の“通り道”を意味します。龍神は“寝床”である櫛の山から、朝な夜な海へと出かけてくる。だから大海へとつながる龍の道の直線上にある岩には、供物を置き龍神に捧げていたのではないかということです。
日向は今日、お昼から雷ごろごろ、龍神様が乱舞しております(;´Д`)

▼「和く!和く!神ingネットワーク」Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka
境内拡張造成工事の後に見つかった神座(さざれ石)のそばで、いつも水がちょろちょろ流れ込み、泥がたまっている場所があったそうです。
新名宮司はこの場所が気になっていて、いつか堀ってみようと思っていましたが、いつも水浸しなので長年そのままになっていました。
しかし平成23年、正月から4月まで雨が一滴も降らず、完全に乾いた時がありました。それで今が機会だと、4月12日から14日の3日間をかけて掘り起こしてみました。
すると中から、長径1m・短径75㎝の卵型の大きな岩が出てきました。下の方に手を突っ込んでみると、どうやら球状になっている。取り出そうにも取り出せない(重さ推定1t)。一体これは何じゃろかい?と。
地質学的には甌穴と言われるものですが、側面には意図的に掘られたではないかと思われる渦巻き状のらせんがあります。
NPO法人「日本巨石文化研究所」の武内一忠氏によれば、丸石は“龍の卵”、貯まった水は“羊水”、すなわち龍神信仰の表れであるとのこと。
これが龍神伝説のはじまり。宮司が2頭の白龍を見た10年後の出来事です。
今は泥が取り除かれ、水の中に龍の玉が眠っていますが、このどこからかしみ出してきて甌穴に注がれる水。一体どこから来ているのだろうと思っていたら、大御神社の東側にある「櫛の山」が源流だったようです。
今は櫛の山と大御神社を道路が分断しているのでたくさんの水は流れてきませんが、以前はもっと脈々と水が流れていたのだろうと言われます。
これはすなわち龍神の“通り道”を意味します。龍神は“寝床”である櫛の山から、朝な夜な海へと出かけてくる。だから大海へとつながる龍の道の直線上にある岩には、供物を置き龍神に捧げていたのではないかということです。
日向は今日、お昼から雷ごろごろ、龍神様が乱舞しております(;´Д`)

▼「和く!和く!神ingネットワーク」Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka
2013年07月25日
龍神(1)
大御神社の新名宮司は毎朝、本殿裏の海で禊をされています。
夜明けの海につかり、心身を清め、海の霊気を受け取ります。
この禊は平成5年7月7日より始められ、どんな天候や体調でも欠かすことなく20年続けられてこられました。
南国宮崎とは言っても、冬の寒さは厳しいものがありますし、肩までつかるほどの深さまでいきますから嵐のときなどは本当に命がけです。
それでも宮司はちゃんと生きていますし(笑)、命を助けられたと感じたこともしばしばあるそうです。
また禊をし始めてから、5年ごとに“おかげ”をいただいていると言います。
禊を始めて5年目の平成10年の正月大寒、宮司がいつものように禊をしていると、水平線から朱色に染まりゆく東の空を、乱舞しながら駆け昇る2頭の白龍が。
その後、これを御祭神からの啓示として「天翔獅子舞」を創作し、翌平成11年例大祭で新しい神事芸能として奉納しました。
そしてさらに10年後に「龍の玉」、いわゆるドラゴンボールが見つかりました。これを皮切りに龍神伝説につながる遺跡が次々発見されています。
宮司は、このことを海に入ることで龍神とつながったのではないかと考えています。
蛇足ですが、私カワノも正月元旦に禊をさせていただきまして(写真はその時の様子です)。たった一度の禊でおこがましいことですが、もしかしたらこのように発信させていただけているのも、少しだけ龍神様とのつながりができたからかもしれません。
ちなみに神武天皇も角と輝く目を持ち、尻に龍尾があり、背中に大きな鱗が生えていたといういわれもあります。
神武天皇舟出の地に、龍神伝説ありですね!
▼「和く!和く!神ingネットワーク」Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

夜明けの海につかり、心身を清め、海の霊気を受け取ります。
この禊は平成5年7月7日より始められ、どんな天候や体調でも欠かすことなく20年続けられてこられました。
南国宮崎とは言っても、冬の寒さは厳しいものがありますし、肩までつかるほどの深さまでいきますから嵐のときなどは本当に命がけです。
それでも宮司はちゃんと生きていますし(笑)、命を助けられたと感じたこともしばしばあるそうです。
また禊をし始めてから、5年ごとに“おかげ”をいただいていると言います。
禊を始めて5年目の平成10年の正月大寒、宮司がいつものように禊をしていると、水平線から朱色に染まりゆく東の空を、乱舞しながら駆け昇る2頭の白龍が。
その後、これを御祭神からの啓示として「天翔獅子舞」を創作し、翌平成11年例大祭で新しい神事芸能として奉納しました。
そしてさらに10年後に「龍の玉」、いわゆるドラゴンボールが見つかりました。これを皮切りに龍神伝説につながる遺跡が次々発見されています。
宮司は、このことを海に入ることで龍神とつながったのではないかと考えています。
蛇足ですが、私カワノも正月元旦に禊をさせていただきまして(写真はその時の様子です)。たった一度の禊でおこがましいことですが、もしかしたらこのように発信させていただけているのも、少しだけ龍神様とのつながりができたからかもしれません。
ちなみに神武天皇も角と輝く目を持ち、尻に龍尾があり、背中に大きな鱗が生えていたといういわれもあります。
神武天皇舟出の地に、龍神伝説ありですね!
▼「和く!和く!神ingネットワーク」Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

2013年07月23日
神座(2)
写真はボウズ山をバックにした神座(かみくら)。
手前に岩が階段状に削られているのをご存知でしょうか。これは実は元からあったもので、最近のものではないそうです。
■古代祭場だった神座
神座の上には「水窪石(みずくぼいし)」と言われる窪みのある石があり、祭場として使われていた形跡が見られます。
神座手前の階段は祭場へと上がるためのものだったのかもしれません。
さて、どのように祈りを捧げていたのかと言うと、水窪石の窪みに貯まった雨水をササで祓い清めるというものでした。祈りを捧げる先は、南十字星。水窪石から南の方角を指す石列や意図的に削ったとみられる目印も残っています。
何に使われていたのかは分かりませんが、神座そのものに「盃状穴(はいじょうけつ)」と言われる窪みも並んでいます。こちらは神座の下からも見て取ることができます。
いずれにしても、古代の人々にとって神座が特別な場所であったことは言うまでもありません。
ちなみに、古代の祭祀形式は、岩上祭祀と洞窟(岩陰)祭祀が主だったようです。大御神社の境内を挟んだ北側の洞窟に鎮座する鵜戸神社がありますから、大御神社には古代の2大祭祀があることになります。
▽さざれ石についての詳細はこちら
http://www.oomijinja.jp/sazareishi/index.htm
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

手前に岩が階段状に削られているのをご存知でしょうか。これは実は元からあったもので、最近のものではないそうです。
■古代祭場だった神座
神座の上には「水窪石(みずくぼいし)」と言われる窪みのある石があり、祭場として使われていた形跡が見られます。
神座手前の階段は祭場へと上がるためのものだったのかもしれません。
さて、どのように祈りを捧げていたのかと言うと、水窪石の窪みに貯まった雨水をササで祓い清めるというものでした。祈りを捧げる先は、南十字星。水窪石から南の方角を指す石列や意図的に削ったとみられる目印も残っています。
何に使われていたのかは分かりませんが、神座そのものに「盃状穴(はいじょうけつ)」と言われる窪みも並んでいます。こちらは神座の下からも見て取ることができます。
いずれにしても、古代の人々にとって神座が特別な場所であったことは言うまでもありません。
ちなみに、古代の祭祀形式は、岩上祭祀と洞窟(岩陰)祭祀が主だったようです。大御神社の境内を挟んだ北側の洞窟に鎮座する鵜戸神社がありますから、大御神社には古代の2大祭祀があることになります。
▽さざれ石についての詳細はこちら
http://www.oomijinja.jp/sazareishi/index.htm
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

2013年07月23日
神座(1)
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の巌となりて
苔のむすまで
国歌「君が代」に歌われる「さざれ石」。大御神社は、その巨大な磐座(いわくら)が見つかったとして一躍有名になりましたが、この磐座が出現したのは、平成15年の境内拡張造成工事の時でした。
大御神社の由緒に天孫降臨で知られるニニギノミコトが大きな岩に立たれ絶景の大海原を眺望されたとあり、新名宮司は30年来いつも周囲を眺めてはその岩を探していたそうです。それでこの巨大なさざれ石が出たときにその岩だと確信され、神座(かみくら)と名づけ注連縄を張り廻らしました。
▽さざれ石発見の経緯と詳細はこちら
http://www.oomijinja.jp/sazareishi/index.htm
■実は、山全体がさざれ石
さざれ石は全国にいくつか見られる場所はありますが、インターネットで検索していただくと、大御神社のしめ縄をかけた神座だけでも相当巨大なものだということが分かります。
それが今回、境内西側(通称:ボウズ山)の塩見川に至る岸壁一帯がさざれ石であり、日本最大の規模であることを知りました。
新名宮司にご案内いただいたのですが、あまりのスケールに感嘆しっぱなしでした。
岩肌には今にも扉が開いて宇宙人が出てきそうなところや、崖下には宇宙船のような巨石もありました。
宇宙の特別な神様は、さざれ石にしか降臨されないという話を聞いたことがあります。こんな大きなさざれ石ですから、きっとたくさんの宇宙の神様が降りて来たんだろうなぁ…
出入りは自由だそうですが、結構な崖っぷちなのでご注意ください( ;∀;)
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

千代に八千代に
さざれ石の巌となりて
苔のむすまで
国歌「君が代」に歌われる「さざれ石」。大御神社は、その巨大な磐座(いわくら)が見つかったとして一躍有名になりましたが、この磐座が出現したのは、平成15年の境内拡張造成工事の時でした。
大御神社の由緒に天孫降臨で知られるニニギノミコトが大きな岩に立たれ絶景の大海原を眺望されたとあり、新名宮司は30年来いつも周囲を眺めてはその岩を探していたそうです。それでこの巨大なさざれ石が出たときにその岩だと確信され、神座(かみくら)と名づけ注連縄を張り廻らしました。
▽さざれ石発見の経緯と詳細はこちら
http://www.oomijinja.jp/sazareishi/index.htm
■実は、山全体がさざれ石
さざれ石は全国にいくつか見られる場所はありますが、インターネットで検索していただくと、大御神社のしめ縄をかけた神座だけでも相当巨大なものだということが分かります。
それが今回、境内西側(通称:ボウズ山)の塩見川に至る岸壁一帯がさざれ石であり、日本最大の規模であることを知りました。
新名宮司にご案内いただいたのですが、あまりのスケールに感嘆しっぱなしでした。
岩肌には今にも扉が開いて宇宙人が出てきそうなところや、崖下には宇宙船のような巨石もありました。
宇宙の特別な神様は、さざれ石にしか降臨されないという話を聞いたことがあります。こんな大きなさざれ石ですから、きっとたくさんの宇宙の神様が降りて来たんだろうなぁ…
出入りは自由だそうですが、結構な崖っぷちなのでご注意ください( ;∀;)
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

2013年07月23日
大御神社
日向灘を背に、伊勢ケ浜の岸壁に立つおごそかな本殿。君が代に詠われる巨大なさざれ石に、龍神信仰を彷彿とさせる龍の玉や登り龍など、埋もれていた古代の事実が今という時を待っていたかのように次々と姿を現し始めています。
そして多くの霊能者やスピリチュアルな方々が次々と訪れ、この場所を中心とした渦が起きているように感じます。
大御神社HP・ご由緒
http://www.oomijinja.jp/history/
今回、新名宮司から、ここには載っていないお話を聞かせていただきました。
■歴史に隠された名前
平成11年、大御神社が文化財に指定された際の調査で、「天照皇太神宮」と書かれた祈願札が出てきました。祈願札というのは、神社が氏子さんに差し上げるお祈りしましたよという印のようです。
それは大御神社がかつて「天照皇太神宮」という名であったことを意味しています。
天照大神をまつる神社は全国約1万4千社ありますが、「天照皇太神宮」という名の神宮は現在、伊勢神宮の内宮のみ。それが日向にあったということなのです。
詳しく調べると、明治時代の「近代社格制度」(神社を等級化する制度)によって、こんな片田舎に「皇大神宮」を名乗る神社があってはいけないということで改名を余儀なくされたようです。そして天照大御神の一部をいただき、現在の「大御神社」という名前になりました。
こうして、日向の「天照皇太神宮」という名前は歴史の裏に隠されてしまいましたが、実は今のように有名になる三十年以上前から、古神道の研究家たちはそのことを突き止めていました。
神様が移されるとき、地名ごと移るのだそうですが、伊勢ケ浜、五十鈴川、日向…大御神社と伊勢神宮の周辺には共通する地名が多くみられます。
2017年前、天照大神が伊勢神宮に鎮まるまでに、歴代天皇がご神体を持ち移動しながらを代々お祀りしていました。そのため伊勢神宮の元宮と言われる神社が全国各地にある理由が分かります。
日向は初代天皇である神武天皇がお船出をした場所です。神武天皇が大和へ入る以前にこの地に天照大神を祀っていたことは想像にたやすいことであり、この大御神社が元々宮というのも納得できる話ではないでしょうか。
今回、新名宮司とお話をさせていただいて面白い話をたくさん聞かせていただきました。一度では書ききれないので、
今後数回に分けて色々とお伝えしていきたいと思います(*^^)v
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka

そして多くの霊能者やスピリチュアルな方々が次々と訪れ、この場所を中心とした渦が起きているように感じます。
大御神社HP・ご由緒
http://www.oomijinja.jp/history/
今回、新名宮司から、ここには載っていないお話を聞かせていただきました。
■歴史に隠された名前
平成11年、大御神社が文化財に指定された際の調査で、「天照皇太神宮」と書かれた祈願札が出てきました。祈願札というのは、神社が氏子さんに差し上げるお祈りしましたよという印のようです。
それは大御神社がかつて「天照皇太神宮」という名であったことを意味しています。
天照大神をまつる神社は全国約1万4千社ありますが、「天照皇太神宮」という名の神宮は現在、伊勢神宮の内宮のみ。それが日向にあったということなのです。
詳しく調べると、明治時代の「近代社格制度」(神社を等級化する制度)によって、こんな片田舎に「皇大神宮」を名乗る神社があってはいけないということで改名を余儀なくされたようです。そして天照大御神の一部をいただき、現在の「大御神社」という名前になりました。
こうして、日向の「天照皇太神宮」という名前は歴史の裏に隠されてしまいましたが、実は今のように有名になる三十年以上前から、古神道の研究家たちはそのことを突き止めていました。
神様が移されるとき、地名ごと移るのだそうですが、伊勢ケ浜、五十鈴川、日向…大御神社と伊勢神宮の周辺には共通する地名が多くみられます。
2017年前、天照大神が伊勢神宮に鎮まるまでに、歴代天皇がご神体を持ち移動しながらを代々お祀りしていました。そのため伊勢神宮の元宮と言われる神社が全国各地にある理由が分かります。
日向は初代天皇である神武天皇がお船出をした場所です。神武天皇が大和へ入る以前にこの地に天照大神を祀っていたことは想像にたやすいことであり、この大御神社が元々宮というのも納得できる話ではないでしょうか。
今回、新名宮司とお話をさせていただいて面白い話をたくさん聞かせていただきました。一度では書ききれないので、
今後数回に分けて色々とお伝えしていきたいと思います(*^^)v
▼Facebookページはこちら!
https://www.facebook.com/kaminghimuka