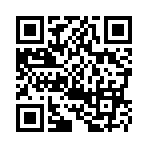2013年12月26日
「日要上人 第五百遠忌」 レポート
「日要上人 第五百遠忌」に参列してきました('ω')
この日のために県内外から集結した僧侶たちによる法要にはじまり、最後は一社二寺(鉾島神社/観音寺[曹洞宗]/妙国寺[日蓮宗])による“経”と“祝詞”の唱和、“南無妙法蓮華経”の中での玉串奉納・・・
宗教・宗派を超えた祈りの姿、町の結集に鳥肌の連続。この機会に立ち会うことができて、本当に感激でした。
きっと、ほとんどの方が「日要上人て誰やねん!?」て感じだと思いますが、亡くなってから500年も語り継がれるということは、本当にすごい方なのだということを改めて実感しました。
日要上人は細島出身で、日蓮宗の本山「妙本寺」の第十一代座主となった偉人です。
今回、その偉業とともに知っていただきたいと感じた“本門寺”というお寺の話をご紹介します。
日要上人は勤皇家としても知られ、当時朝廷に謁見することが許された数少ない人物のひとりでもありました。
妙本寺には、日要上人が天皇から賜った論旨(手紙のようのもの)が今も残されており、千葉県の文化財に指定されています。
そこには“お手紙ありがとう、またご意見をどんどんください、私のことをいつも思ってくれてありがとう”といった内容が綴られており、「恐恐謹言」という言葉で結ばれています。これは目下の人から目上の人に“おそれながらつつしんで申し上げる”の意。
天皇はあまり使わない言葉が日要上人には使われているのです。
その綸旨の中で天皇は、“妙本寺の日要上人”に対して“本門寺の日要上人”と表現していますが、実は“本門寺”とは実在しないお寺。
かつて、日本に仏教が伝わった拠点として東大寺・大宰府・薬師寺がありましたが、古い開眼は役に立たないということで、桓武天皇の時代に比叡山延暦寺が正式な開眼として仏教の拠点になりました。
しかし、ここでも鎌倉時代になって分派統合が行われ、これではいけないと、すべての仏法・世界の宗教思想が和合して一つの大いなる聖地を目指そうと言って、その理想の聖地を「本門寺」と名付けました。
ですから、本門寺というお寺は、当時はもちろん未だもってできていません。
天皇が日要上人に対して“本門寺の日要上人”と表現したのは、もし本門寺ができたらそこの住職にふさわしいと考えていたことを意味しています。
今回、日要上人の五百遠忌に際して、宗教・宗派を超えた取組ができたということは因縁とも呼べることであり、また次なる五百年、新たな時代の幕開けを感じさせるものとなったような気がしました!

この日のために県内外から集結した僧侶たちによる法要にはじまり、最後は一社二寺(鉾島神社/観音寺[曹洞宗]/妙国寺[日蓮宗])による“経”と“祝詞”の唱和、“南無妙法蓮華経”の中での玉串奉納・・・
宗教・宗派を超えた祈りの姿、町の結集に鳥肌の連続。この機会に立ち会うことができて、本当に感激でした。
きっと、ほとんどの方が「日要上人て誰やねん!?」て感じだと思いますが、亡くなってから500年も語り継がれるということは、本当にすごい方なのだということを改めて実感しました。
日要上人は細島出身で、日蓮宗の本山「妙本寺」の第十一代座主となった偉人です。
今回、その偉業とともに知っていただきたいと感じた“本門寺”というお寺の話をご紹介します。
日要上人は勤皇家としても知られ、当時朝廷に謁見することが許された数少ない人物のひとりでもありました。
妙本寺には、日要上人が天皇から賜った論旨(手紙のようのもの)が今も残されており、千葉県の文化財に指定されています。
そこには“お手紙ありがとう、またご意見をどんどんください、私のことをいつも思ってくれてありがとう”といった内容が綴られており、「恐恐謹言」という言葉で結ばれています。これは目下の人から目上の人に“おそれながらつつしんで申し上げる”の意。
天皇はあまり使わない言葉が日要上人には使われているのです。
その綸旨の中で天皇は、“妙本寺の日要上人”に対して“本門寺の日要上人”と表現していますが、実は“本門寺”とは実在しないお寺。
かつて、日本に仏教が伝わった拠点として東大寺・大宰府・薬師寺がありましたが、古い開眼は役に立たないということで、桓武天皇の時代に比叡山延暦寺が正式な開眼として仏教の拠点になりました。
しかし、ここでも鎌倉時代になって分派統合が行われ、これではいけないと、すべての仏法・世界の宗教思想が和合して一つの大いなる聖地を目指そうと言って、その理想の聖地を「本門寺」と名付けました。
ですから、本門寺というお寺は、当時はもちろん未だもってできていません。
天皇が日要上人に対して“本門寺の日要上人”と表現したのは、もし本門寺ができたらそこの住職にふさわしいと考えていたことを意味しています。
今回、日要上人の五百遠忌に際して、宗教・宗派を超えた取組ができたということは因縁とも呼べることであり、また次なる五百年、新たな時代の幕開けを感じさせるものとなったような気がしました!

Posted by カワノ at 11:30│Comments(0)
│日向岬・市街地周辺