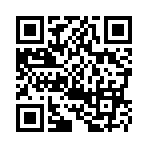2013年09月02日
「天与の使命である。」
美々津港横に立つ、海軍発祥の碑。
作者は彫刻家、故・日名子実三(ひなこじつぞう、1892年‐1945年4月25日、大分県臼杵市出身)。
八咫烏に導かれ、歴史に名を残した彫刻家でした。
この海軍発祥の碑は、神武天皇がお船出した(※)美々津の地は“日本海軍発祥之地”として、紀元二千六百年記念事業の一環で建立されたもの。
また、日名子実三は紀元二千六百年記念事業において、宮崎市の平和台公園にある「平和の塔」のデザインも手掛けています。(平和台のふもとに皇宮屋がある)
「平和の塔」は、元の名を「八紘之基柱(あめつちのもとはしら)」と言い、『日本書紀』で神武天皇が天皇に即位した際の「掩八紘而爲宇(あめのしたをおおひていえとなさむ、またよろしからずや=世界がひとつの屋根の下の家族のように仲良く暮らすなら、なんと楽しく嬉しいことだろう)」という詔に由来しています。
ちなみに平和の塔には手水舎がありますが、その水盤は日向市美々津産の岩を使用し、前面に当時の相川勝六知事の筆で「美々津」と彫られています。これは、神武天皇が美々津からお舟出したことを表しているということです。
日名子実三は基柱の提唱者である当時の宮崎県知事・相川勝六と出会い、基柱の話を受けて自ら「報酬は一文もいらないから、是非私にやらせてほしい」と申し入れました。
そして当時、新進の彫刻家であった日名子実三が手掛けることとなり、「これは天与の使命である。」と神助を得て渾身の仕事を行いました。
この後、日名子実三は日本サッカー連盟のシンボルマークとなっている、日本神話の中で神武天皇を道案内したと言われる鳥・八咫烏(やたがらす)をモチーフにしたエンブレムのデザインをしたことで知られます。
※宮崎県の高原で幼少期をすごした神武天皇は、15歳で皇太子となり宮崎市内の皇宮(宮崎神宮摂社)に宮を移すと、45歳のときに東遷に発ちます。そして陸路で美々津まで行き、そこで水軍を整えて再び進発したと伝えられています。

作者は彫刻家、故・日名子実三(ひなこじつぞう、1892年‐1945年4月25日、大分県臼杵市出身)。
八咫烏に導かれ、歴史に名を残した彫刻家でした。
この海軍発祥の碑は、神武天皇がお船出した(※)美々津の地は“日本海軍発祥之地”として、紀元二千六百年記念事業の一環で建立されたもの。
また、日名子実三は紀元二千六百年記念事業において、宮崎市の平和台公園にある「平和の塔」のデザインも手掛けています。(平和台のふもとに皇宮屋がある)
「平和の塔」は、元の名を「八紘之基柱(あめつちのもとはしら)」と言い、『日本書紀』で神武天皇が天皇に即位した際の「掩八紘而爲宇(あめのしたをおおひていえとなさむ、またよろしからずや=世界がひとつの屋根の下の家族のように仲良く暮らすなら、なんと楽しく嬉しいことだろう)」という詔に由来しています。
ちなみに平和の塔には手水舎がありますが、その水盤は日向市美々津産の岩を使用し、前面に当時の相川勝六知事の筆で「美々津」と彫られています。これは、神武天皇が美々津からお舟出したことを表しているということです。
日名子実三は基柱の提唱者である当時の宮崎県知事・相川勝六と出会い、基柱の話を受けて自ら「報酬は一文もいらないから、是非私にやらせてほしい」と申し入れました。
そして当時、新進の彫刻家であった日名子実三が手掛けることとなり、「これは天与の使命である。」と神助を得て渾身の仕事を行いました。
この後、日名子実三は日本サッカー連盟のシンボルマークとなっている、日本神話の中で神武天皇を道案内したと言われる鳥・八咫烏(やたがらす)をモチーフにしたエンブレムのデザインをしたことで知られます。
※宮崎県の高原で幼少期をすごした神武天皇は、15歳で皇太子となり宮崎市内の皇宮(宮崎神宮摂社)に宮を移すと、45歳のときに東遷に発ちます。そして陸路で美々津まで行き、そこで水軍を整えて再び進発したと伝えられています。

Posted by カワノ at 16:54│Comments(0)
│美々津周辺